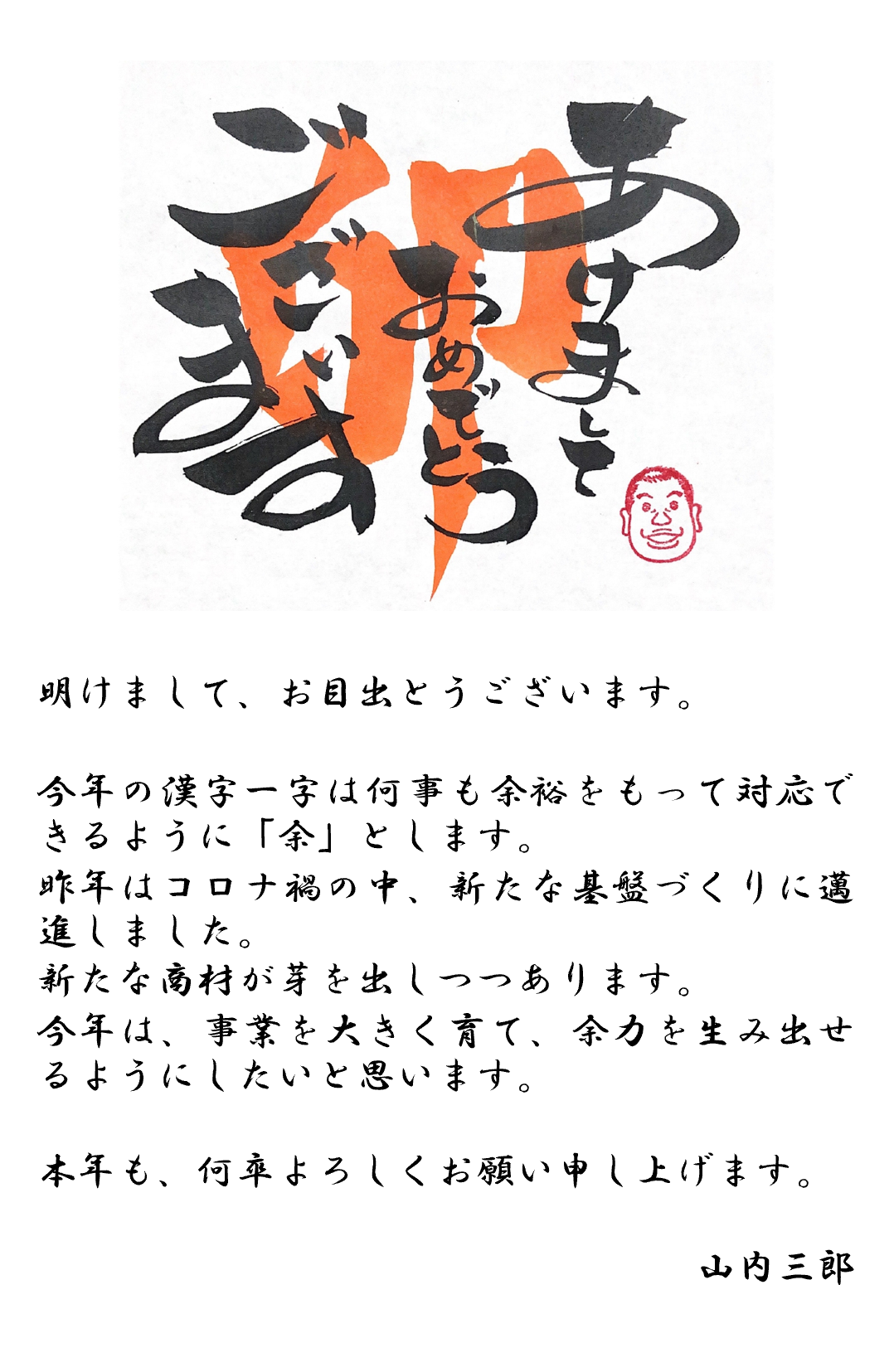強みをいかす
ChatGPTなどを使うと、文章はもちろんですが、
もう疑似的に人がしゃべることと同じようなことができるようになってきています。
ただ、過去の蓄積について相対的にしゃべることはできても、
今のことを専門家のようにしゃべることはまだ、不得意のようです。
人がAIと違った仕事をしていくには、
何か専門性を持つことが大事であるような気がしてきました。
人がこれから仕事をしていくことについて、「楽しさ」などを強調することが多いですが、
楽しさとは、やはり自分の強みを生かしていくことだと思います。
自分のやりたいことは目標ですが、その中で、強みを生かすとは、
全体に波及しないことも多くあると思います。
やりたいことの一部を担うこともあるとは思いますが、
それは、それで達成感があると思います。
やりたいことがあれば、多少自分に必要なスキルや知識が足りなくても、
それを実現する継続的な努力は生まれると思います。
P.F.ドラッカーは、企業経営やマネジメントに関する著書の中で、
「強み(Strength)」という概念を提唱しました。
彼によると、「強み」とは、組織や個人が本来持っている優位性や長所のことを指します。
つまり、企業や個人が自分たちにとって最も得意なことや、最も高い成果を出せる能力を把握し、
それに注力することで成功することができるとされています。
しかしながら、自分で強みを理解していないことが多いとも言っています。
ドラッカーは、「強み」の発見や発展には以下のステップが必要であるとしています。
(1)自己分析:
自分たちがどのような能力や資源を持っているかを把握する。
(2)外部分析:
市場や競合環境など、外部の状況を分析し、自分たちがどのような環境で
最も強みを発揮できるかを考える。
(3)強みの発掘:
自己分析や外部分析を基に、自分たちが最も得意なことや、
最も高い成果を出せる能力を見つけ出す。
(4)強みの発展:
強みをより伸ばすために、その能力をさらに磨き、
新たな取り組みに挑戦することで、競争優位性を確立する。
このように、ドラッカーによる「強み」の概念は、企業や個人が自らの強みを見つけ、
それに集中することで成功を収めることを提唱しています。