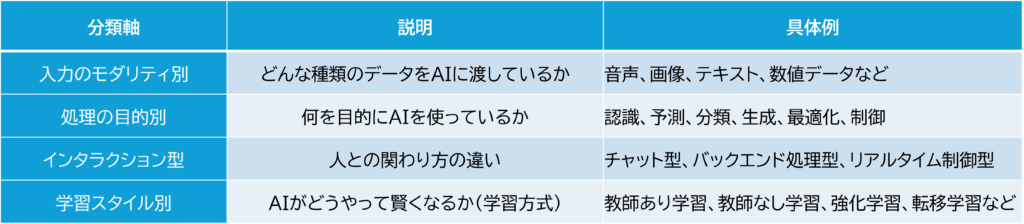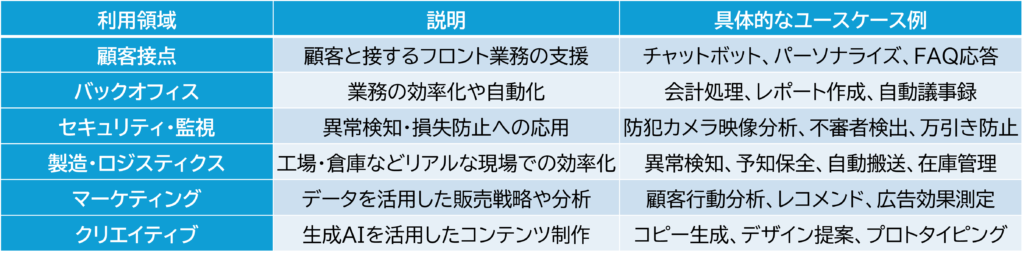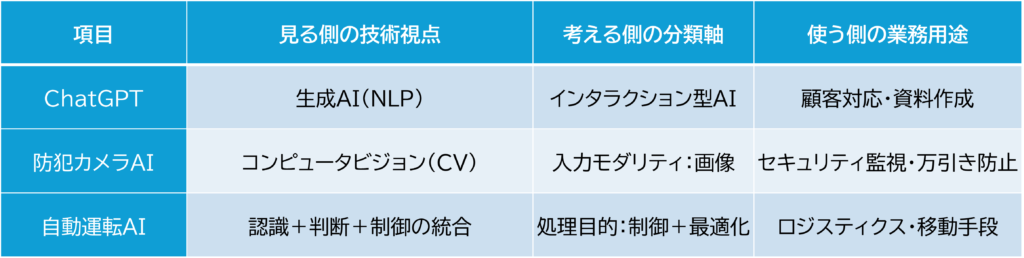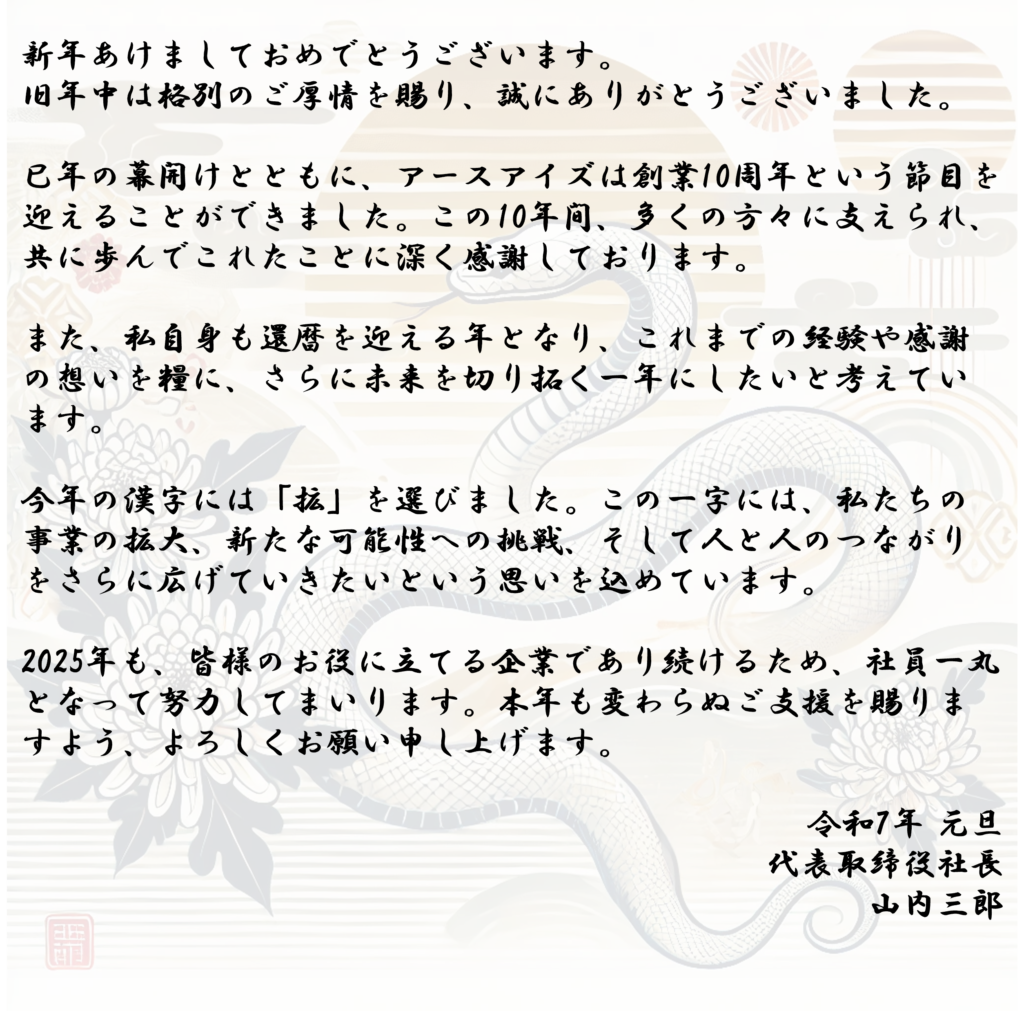サブロー風進化論:ダーウィンを超えて? 魂のバトン”が繋ぐ、生命のミステリー
こんにちは、サブローです。
今日は皆さんと一緒に、生命の進化という壮大な謎について、少し思索を深めて
みたいと思います。
かのチャールズ・ダーウィンは、「最も知的な種が生き残るのではない。最も強
い種が生き残るのでもない。唯一生き残るのは、変化に対応できる種である」と
いう言葉を残しました。この言葉、とても深くて、なるほどなぁと思わされます
よね。
ただ、私がずっと心に引っかかっているのは、この「変化に対応する」という部
分なんです。一つの生命が、その一生の中で環境の変化に合わせて能力を変える…
というのは、まだ理解できる気がします。
でも、それが世代を超えて、まるで何か大きな目的を共有しているかのように、
特定の方向へ向かって自分の体形や姿を変化を続けていくというのは、一体どう
いうことなのでしょうか。
例えば、昆虫や生物の擬態です。
昆虫がまるで葉っぱそのものに見えるようになったり、魚が周りの岩や砂の色に
完璧に溶け込んだり、カメレオンが背景の色と同化したり、ましてや、あの小さ
なフグが強力な毒を持つようになり、「食ったら死ぬぞ・・・・」ってすごいで
すよね。さらには、毒蛇のように獲物を捕らえるために毒を持つとかデンキウナ
ギのように電気を発生させるとか?それは、「祈ったって出来そうもない」こと
をできる動植物がいます。
これらが、単なる「偶然の積み重ね」を世代を超えて変化を求めるだけで、でき
るようになるのでしょうか?私には、どうしてもそうは思えないのです。なんだ
か、そこには「偶然」だけでは片付けられない、何か大きな意志のようなものが
働いているように感じてしまうのですよね。
進化の過程には、きっと数えきれないほどの失敗があった筈です。でも、生き残
ることができなければ、その失敗から学ぶことはできません。しかしながら、上
記のような擬態をするのであれば、「致命傷」に近いくらいの経験をして、何と
か生き残る工夫を必死にしなければ、自らの身体を擬態化するなどはできないよ
うに思えるのです。死んでしまえば、その種のDNA等は到底引き継げません。
それなのに、どうしてあんなにも複雑で精巧な擬態や防御機能が、まるで誰かが
デザインしたかのように生まれてくることができたのでしょうか。
ある方が、こんな魅力的な仮説を話してくれました。
「もし、“魂”というものが存在して、その魂が過去の経験や切実な願いを記憶し、
次の新しい命へとその記憶を引き継いでいるとしたら…?
肉体が滅んでも、体が死んでも引き継げる魂レベルで蓄積された経験こそが、次の
世代の進化の“青写真”になっているのかもしれないよ」と。
これは、かつてラマルクが提唱した「獲得形質の遺伝」という考え方に、「魂の転
生」という、どこか懐かしくも新しい視点を加えたような、非常にユニークで心惹
かれるお話だと思いませんか?もし仮に、生まれ変わり、死に変わりしても魂は引
き継がれ、同じ生物に何度も、生まれ変わり、何度も、同じ死に方をしていれば、
「もう、同じ死に方したくない・・・」と思えれば、擬態などが生まれる気がしま
す。
遺伝子に“想い”は宿るのでしょうか?
現代科学の視点から見れば、遺伝子はあくまで化学物質の集まりであり、脳もまた、
電気信号や化学反応によって機能する生物的な器官です。
そこに「意思」や「魂」といった非物質的なものが介在すると考えるのは、少し飛
躍があるのかもしれません。
でも、私たちが生命の営みの中に感じる、あの言葉では言い表せない「何か」
–それは、今の科学的な分析だけでは捉えきれない、ミステリアスで、温かく、そ
して豊かな感覚だとは思いませんか?真実は、もしかしたら一つではないのかもし
れません。あるいは、まだ私たちの目には見えていない、もっと大きな全体像の一
部を、私たちはそれぞれ違う角度から見ているだけなのかもしれません。
大切なのは、こうして「なぜだろう?」「どうしてだろう?」と問いを持ち続ける
こと。そして、生命の持つ計り知れない不思議さ、その奥深さに、心を動かし続け
ることなのではないかな、と私は思うのです。